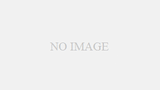「眠っても疲れが取れない」「夜中に何度も目が覚める」
――そんな悩みを抱える人は少なくありません。
厚生労働省の調査によると、日本人の約4割が睡眠に何らかの不満を感じています。
本記事では、最新の研究と実体験をもとに、質の良い睡眠を取るための習慣4選をご紹介します。
今日からできる具体的な改善法を知り、朝スッキリ目覚める毎日を手に入れましょう。
睡眠改善の基本原則とは?
質の良い睡眠は、時間の長さだけではなく質で決まります。
厚労省の「健康づくりのための睡眠指針」では、規則正しい生活リズム・快適な睡眠環境・ストレス管理の3つが重要とされています。
睡眠の質を高めるには、
- 入眠がスムーズであること
- 夜中に何度も目覚めないこと
- 深い眠りを十分に確保できること
が条件です。
これを支えるのが体内時計の安定と副交感神経の働きです。2024年の米国睡眠医学会(AASM)の研究でも、日中の活動量と光の浴び方が睡眠の質に直結すると報告されています。
まずは自分の睡眠パターンを知ることが第一歩です。スマホアプリやウェアラブル端末で記録すると、改善の方向性が見えやすくなります。
習慣① 朝日を浴びて体内時計をリセット
人間の体は、太陽の光によって体内時計が調整されることがわかっています。
太陽の光は、体の中の約24時間リズムを毎日正確にリセットする「時報」のような役割を果たしていて、これによって人間は昼と夜に合わせて活動・休息ができるようになっています。
- 体内時計の役割
人間を含む多くの生物は約24時間周期で動く「体内時計」を持っています。この体内時計は睡眠や覚醒、ホルモン分泌、体温調整など様々な生理機能をリズムよくコントロールしています。 - なぜ外部の光が重要?
体内時計は完全に正確ではなく、だいたい24時間より少し長かったり短かったりします。だから、毎日リセットしないとズレてしまいます。
そのリセットの役割を果たすのが太陽光、特に朝の光です。光は目の網膜にある特別な細胞(光受容細胞)で感知され、脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)という体内時計の中枢に伝えられます。 - 体内時計の調整
視交叉上核は光の情報を受けて体内時計を「今は朝だよ」「昼だよ」と認識し、体内時計のタイミングを調整します。これによって、体のリズムが外の昼夜サイクルにぴったり合うようになるのです。 - なぜ合わないと困る?
もし体内時計が外の時間とズレてしまうと、睡眠障害やホルモンバランスの乱れ、集中力低下、免疫機能の低下など健康に悪影響が出ます。だから、太陽の光を使って毎日調整することが生きやすさに繋がっています。
米ハーバード大学の研究では、朝起きてから30分以内に太陽光を浴びると、睡眠を促すメラトニンの分泌リズムが安定することがわかっています。これが乱れると、夜に眠気が来ず、質の低い睡眠になってしまいます。
簡単に習慣にする方法としては、朝の散歩やベランダでの深呼吸、窓際で朝食をとるのもいいでしょう。
習慣② 寝る90分前の入浴で深部体温をコントロール
「入浴はリラックスできるから良い」と聞いたことはありませんか?
実はそれ以上に、深部体温を下げる準備としても効果的です。
- 深部体温とは?
深部体温とは、体の内部(脳や内臓など)の温度のこと。通常、眠りにつく前にこの深部体温がゆっくり下がることで、睡眠スイッチが入るサインになります。 - 入浴と体温の関係
お風呂に入ると、まず体の表面(皮膚)の温度が上がります。これによって血管が広がり(血管拡張)、体の表面から熱が放散されやすくなります。 - 深部体温が下がるメカニズム
入浴後、体が皮膚の熱を外に逃がそうとするので、結果的に体の中心部(深部)の温度が下がります。これが「深部体温の低下」です。 - 深部体温の低下と眠気の関係
研究でわかっているのは、眠る直前に深部体温が下がると、脳が「もう休みの時間だな」と認識し、メラトニン(睡眠ホルモン)が分泌されやすくなること。これが自然な眠気を誘発し、スムーズに眠りにつながります。
東京医科大学の研究によると、就寝90分前に40℃のお湯に15分浸かると、深部体温が下がりやすくなり、自然な眠気が促されます。入浴後はスマホやPCの使用を控え、照明も少し落として副交感神経を優位にしましょう。
習慣③ 寝室環境を“睡眠専用空間”に整える
寝室は「眠るための場所」という条件付けがとても大切です。
なぜ寝室を“睡眠専用空間”にすると睡眠の質が向上するのか?
- 脳が寝る場所として認識しやすくなる
寝室を「寝るためだけの場所」にすることで、脳がその空間に入ると「もう休む時間だ」と自然にスイッチを切り替えやすくなります。 - 覚醒刺激を減らせる
スマホやテレビ、仕事の道具などがあると「やらなきゃ」と脳が覚醒しやすく、寝つきが悪くなります。専用空間ならそうした刺激を減らせます。 - 環境のリズムを整えやすい
寝室の照明や温度、音などを睡眠に最適な状態に統一でき、体内時計や体温調節がスムーズになります。
寝室を“睡眠専用空間”に整える方法
- 寝室での行動を「睡眠」と「休息」だけに限定する
・寝スマホやパソコンは寝る前に使わない
・読書やリラックスだけにする
・仕事や食事は別の部屋で行う - 照明を工夫する
・寝る1時間前からは間接照明などの暖色系の薄暗い灯りにする
・寝室の明かりは完全に消すか、遮光カーテンで外の光をシャットアウトする - 温度・湿度を適切に保つ
・夏は涼しく、冬は暖かく(理想は約18〜22℃)
・湿度は50〜60%を目安にすると快適 - 騒音対策をする
・防音カーテンやホワイトノイズ(自然の音など)を利用する
・耳栓を使うのも効果的 - ベッドや寝具を快適に
・マットレスや枕は自分の体に合った硬さ・高さにする
・シーツやパジャマは通気性の良い素材を選ぶ - 寝室の整理整頓
・物が散らかっていると脳がリラックスしにくいので、シンプルで整った空間を保つ
寝室の温度が18〜22℃だと結構低めのイメージがありますが、米国CDCは、遮光・防音・温湿度(18〜22℃・湿度40〜60%)が質の高い睡眠に最適としています。ただ、人それぞれなので、快適と思える室温・湿度を探してみましょう。
そして、寝室に仕事道具やスマホを持ち込まず、眠りと関係のない刺激を排除しましょう。
習慣④ 就寝前のルーティンで脳をリラックスモードに
脳が「これから寝る」と認識するためには、就寝前のルーティンが有効です。
- マインドフルネス瞑想(1〜5分)
目を閉じて呼吸に意識を集中。息を吸って、吐いて…をゆっくり繰り返すだけ。雑念が浮かんでもOK。心が落ち着きます。 - 読書(10〜15分)
スマホや電子書籍ではなく、紙の本がおすすめ。内容は難しくない、好きなジャンルでOK。脳が自然に落ち着きます。 - 軽いストレッチ(5分程度)
首や肩、腕をゆっくり伸ばす。強い運動は避けて、呼吸を止めずにゆったりと行いましょう。血行が良くなりリラックス。 - 深呼吸エクササイズ(2〜3分)
鼻からゆっくり吸って、口からゆっくり吐く。吐く時間を少し長めにすると副交感神経が優位に。呼吸法は色々あるので、自分に合ったものをチョイス。僕の場合は、鼻から3秒かけて息を吸って、口から7秒かけて吐くロングブレスが合いました。
マインドフルネスや読書、軽いストレッチは副交感神経を優位にし、入眠をスムーズにします。就寝前30分は「デジタルデトックス時間」として、照明を落とし、静かな時間を過ごしましょう。
睡眠の質を下げるやってはいけないNG習慣
- 寝る直前のスマホ・パソコン使用
画面のブルーライトがメラトニン(眠りを促すホルモン)の分泌を抑制し、寝つきが悪くなる。さらに、情報過多で脳が興奮し覚醒状態に。 - 就寝直前のカフェイン摂取(コーヒー・エナジードリンクなど)
覚醒作用が強く、寝つきを悪くし深い睡眠を妨げる。カフェインは体内に数時間残るため影響が長引く。 - 寝る直前のアルコール摂取
入眠は早まるが睡眠の後半で覚醒しやすくなり、レム睡眠が減少。睡眠の質全体が低下する。 - 就寝前の激しい運動
交感神経が刺激されて心拍数が上がり、体温も上昇。リラックス状態になりにくく、寝つきが悪くなる。 - 寝る前の大量の飲食(特に脂っこいものや甘いもの)
消化にエネルギーが使われ、胃腸が活発に動くことで寝つきが悪くなる。夜間の胃もたれや不快感も。 - 寝室でのテレビや仕事
脳が「休む場所」として認識しにくくなり、覚醒状態を引き起こしやすい。睡眠スイッチが入りにくい。 - 不規則な就寝・起床時間
体内時計が乱れ、自然な眠気が起こりにくくなる。睡眠リズムが崩れ、疲労感が残りやすい。
これらのNG習慣は、脳や体がリラックスモードに切り替わるのを妨げるため、眠りの質が低下します。寝る前の行動を見直して快適な睡眠環境を作ることが大切です。
今からできる!睡眠改善習慣チェックリスト
- 朝起きたらカーテンを開けて日光を浴びる
- 就寝90分前に入浴
- 寝室は暗く静かに保つ
- 寝る前は読書や呼吸法でリラックス
- スマホはベッドから離す
今日ご紹介した睡眠改善のコツは、どれも「今からできる」シンプルな習慣ばかりです。
毎日の小さな積み重ねが、やがて質の高い眠りとなってあなたの健康やパフォーマンスを支えてくれます。
まずは、朝の光を浴びることや、寝る90分前の入浴、寝室環境の見直しなど、できそうなことから一つずつ始めてみてください。
また、避けるべきNG習慣にも意識を向けることで、よりスムーズに睡眠の質を改善できます。
質の良い睡眠は、毎日の生活の質そのものを大きく変える力があります。
今日のこの記事が、あなたの快適な眠りと明るい朝への第一歩になれば幸いです。
「Learn from yesterday, live for today, look to tomorrow. (昨日から学び、今日を生き、明日に期待しよう)」